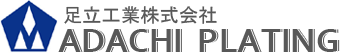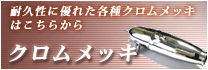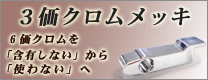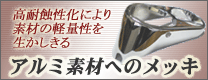![]()
1
![]()
素材入荷
2
![]()
前加工(バフ研磨、バレル研磨、ブラスト処理 等)
3
![]()
有機洗浄
4
![]()
治具付け
5
![]()
前処理(アルカリ洗浄、酸処理 等)
6
![]()
下地メッキ処理(ストライク銅、ストライクニッケル、ジンケート 等)
7
![]()
中間メッキ処理(青化銅、硫酸銅、ダブルニッケル、サチライトニッケル 等)
8
![]()
仕上メッキ処理(クロム、3価クロム、硬質クロム、金 等)
9
![]()
治具外し
10
![]()
検査、包装・出荷
![]()
青化銅
7000L
1基
硫酸銅
2000L
1基
半光沢ニッケル
4000L
2基
光沢ニッケル
4000L
2基
光沢ニッケル
1500L
2基
サチライトニッケル
1000L
1基
ジュールニッケル
600L
1基
装飾クロム
2500L
1基
装飾クロム
650L
1基
硬質クロム
600L
1基
3価クロム(ホワイト)
600L
1基
3価クロム(トワイライト)
600L
2基
フラッシュ金
200L
1基
スズ
400L
1基
黒染め
65L
4基
アルミの前処理
1式
デジタルマイクロスコープ
1基
螢光X線微小部膜厚計
1基
電解式膜厚計
1基
メッキの加工工程
メッキには大きく分けて「仕上げのメッキ」、「中間層のメッキ」、「下地のメッキ」があります。ここでは代表的なメッキの種類であるクロムメッキを例に、メッキの加工工程をご説明致します。
(1)仕上げのメッキ
クロムメッキは仕上げメッキとして使用され、イオン化したクロムを金属クロムに変換して素材の表面に析出させます。金属クロム層を表面に形成することにより、耐蝕性が向上します。 また、通常のクロムメッキのビッカース硬度は800HV程度ですが、硬質クロムメッキを使用すれば、1000HV程度まで硬さを向上させる事も出来ます。
(2)中間層のメッキ
耐蝕性を向上させる、一番の決め手は中間層のメッキです。通常中間層のメッキにはニッケルが使用されますが、耐蝕性を上げるには、ニッケルメッキ層の硫黄(S)の含有量をコントロールし、異なる硫黄含有量の層を多層で形成します。これにより、メッキ層間に電位差が生まれ、相対的に電位の低い層が犠牲となることにより、素地方向への腐蝕を緩慢にして、耐蝕性を向上させることが出来ます。 また、これに加えて非電導性の微粒子をニッケルと共に析出させ、この上に 仕上げメッキを施す「マクロポーラス」と呼ばれる手法があります。これは導通部分と非導通部分の組み合わせでマイクロポーラス構造を作り、結果として 腐蝕電流を極小化して分散させ、耐蝕性を向上させるものです。
(3)下地のメッキ
メッキと素材の密着が強固であることは、メッキに求められる最も基本的な品質です。そしてこの密着性の決め手となるのが「下地のメッキ」です。下地のメッキには素材に合わせて色々な種類があります。アルミ素材であればZn合金とニッケル。亜鉛、鉄、真鍮素材であれば銅。ステンレスであればストライクニッケル等、最初の「下地メッキ」が変わってきます。また同じアルミ素材であっても、純粋なアルミなのか、他にどんな金属が混じっているのかによって処理の仕方が変わってきます。この様にそれぞれの金属に合わせた「下地メッキ」を施すことにより、メッキの密着性を確保することが重要です。